どうも!ととぽんです!!
前回は本格的なお遍路さんの持ち物などをご紹介しました。
今回は第4弾、基本的な参拝方法やマナー、やってはいけないことなどをご紹介します。
基本的な参拝の流れ
まず霊場に入る際に!
境内(山門の向こう側)は仏さまの聖域なので、踏み入れさせて頂くという意味を込めて山門(仁王門)の前で合掌、一礼を行い境内に入りましょう。
手洗い所へ!
手洗い所とは?神社仏閣には水が溜められた所がありますね!(雑)
そこでまず身を清めます。 手を洗い、口をすすぐことによって身体の外と内を清めます。
左手→右手の順番に水をかけ、左手で受けた水で口をすすぎ、 残りの水で柄杓の柄を流してすすぎましょう。
鐘のところに向かおう!

鐘は参拝前の合図ともされています。
鐘が自由に撞けるところでは お参りの前に1度だけ撞きましょう!
もし撞き忘れたとしても帰る際は撞かないでくださいね。
理由は、”出る鐘”(出るとき(帰るとき)に打つ鐘)が「出金」ともとれるので撞きません。
また、死者を送る鐘を「でがね」と呼ぶため、撞かないでくださいね。
鐘は、その音色を仏様に届けるものなので、大きい音ではなく、音色を奏でましょう。
撞いたあとは撞木が鐘に何度も当らない様にしましょう!
いよいよ本堂へ!
いよいよ本堂へ向かいます!
献灯、献香、納札を納めます。鐘を打ち、お賽銭を納めたのち、礼拝、お経を奉納しましょう。
納礼は納礼箱、写経は写経箱に納めます。
続いては大師堂へ
本堂と同じ手順で献灯~お経奉納までを行いましょう。
本堂と大師のお参りを終え、時間の余裕があり他のお堂があればお参りしましょう。
最後に納経所へ◎

参拝を全て終え、納経所でお納経(ご朱印)を頂きましょう。
基本的には参拝後にお納経(ご朱印)を頂きますが、納経時間が終了直前の場合は、霊場にその理由を告げ、参拝前にお納経を受けることができます。
次の霊場へ
始めと同じように、山門(仁王門)で仏様に感謝の意を込めて合掌、一礼をして境内を出ましょう。
次の霊場でも同じ手順で参拝を行いましょう!
やってはいけないこと
お遍路さんに際し、やってはいけないことや注意点がありますのでご紹介します。
戻り鐘
先ほどもお話ししましたが、戻り鐘はやめましょう。
もし撞き忘れたとしても帰る際は撞かないでください。
理由は、”出る鐘”(出るとき(帰るとき)に打つ鐘)が「出金」ともとれるので撞きません。
また、死者を送る鐘を「でがね」と呼ぶため、撞かないでくださいね。
撞いたあとは撞木が鐘に何度も当らないようにすることもマナーとして心得ておきましょう。
納経のみ 又は 拝礼前に納経
お遍路さんには必ず納経があると思いますが、仏様や弘法大師様に読経する前に納経はやめましょう。
また、拝礼せず納経のみも徳が薄まる上にマナーとしても好まれたものではありませんよね。
お遍路さんの目的を再確認してください。
基本的にどこの札所も納経のみや拝礼前の納経はいただけない所が殆どです。
注意書きとして納経所に掲示している場合も多いので、基本として心得ておきましょうね。
読経は端で
読経を行う際は正面を避け、端でおこないましょう。
他に参拝される方に気を配りながら思いやりの精神を忘れないように譲り合いましょうね。
お賽銭は投げない
お賽銭を入れる際は投げ込まずそっと入れましょう。
あくまでもお礼や感謝の気持ちとして入れますので、心を込めてそっと入れるのがマナーです。
両替え
事務所や納経所で両替をお願いするのは控えましょう。
事前に準備しておくのがマナーです。
両替用として準備してくださっている納経所もありますので、そのような場合は準備されているものと替えていただきましょう。
ここまでご観覧いただきありがとうございます!
今回は参拝方法や注意点などについてまとめました。
お遍路さんは仏様や弘法大師様とひとつになるとても素晴らしい行いですので、全ての方が気持ちよく巡礼できることが一番ですよね。
次回からはいよいよ各霊場についてご紹介していけたらと思いますのでよろしくお願いします☆
ブログ村に参加しています◎
応援よろしくお願いいたします。
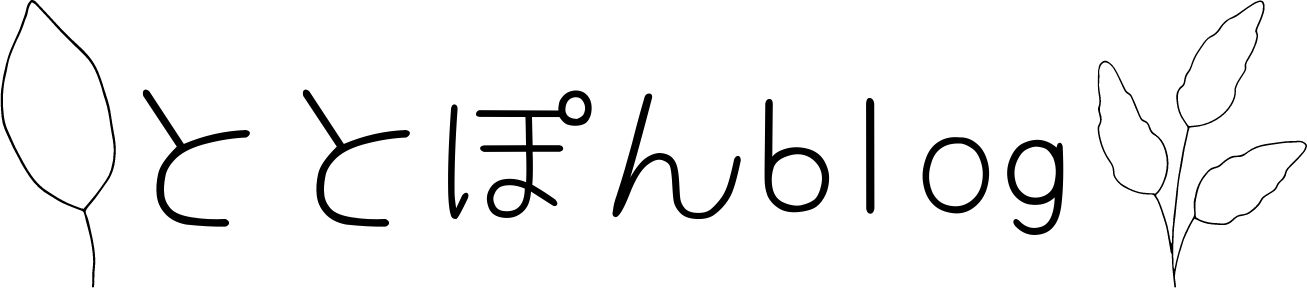
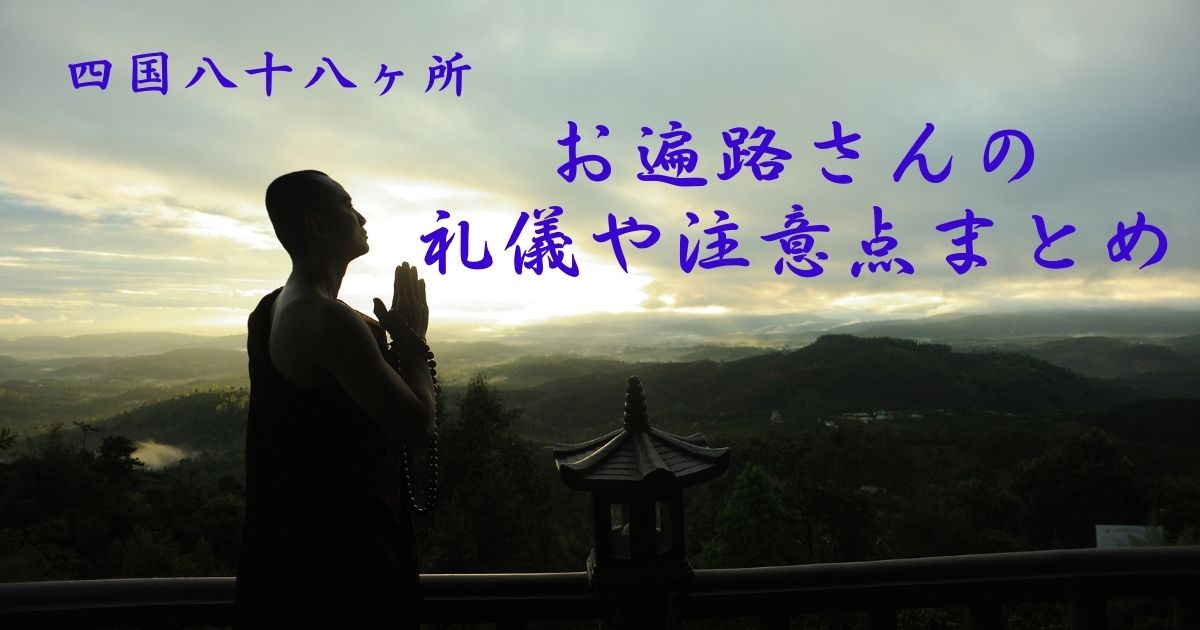


コメント
自分もお遍路を回っていますが、礼儀などできてない事が多々ありました。お恥ずかしい…。お陰でこれからは、恥をかかずにまわれます!ありがとうございます!
コメントありがとうございます!私も記事をまとめながら色々と調べていると知らないことがまだまだ沢山あります。自分自身が勉強になった、知れてよかった情報を発信していけたらと思います☆共に楽しみながらお遍路進みましょうね。